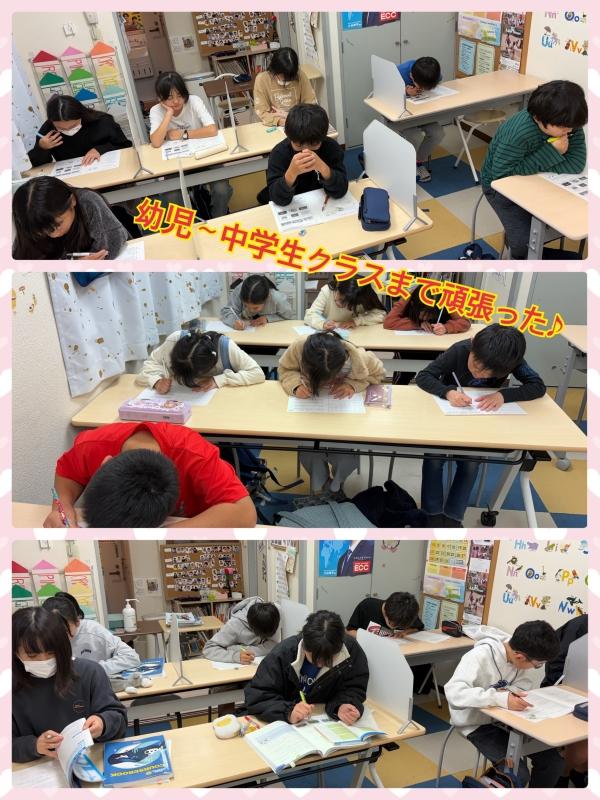映画「小学校 それは小さな社会」

生徒さんがでているというドキュメンタリー映画を見に行ってきました!
「小学校 それは小さな社会〜The Making of Japanese~」
いつも保育園送迎時に前を通る小学校が舞台で、近所の公園や駅などが出てくるだけでワクワクでしたが、改めて日本の学校ってこうだったけなと、いつも息子や生徒さんたちが通っている学校について考えさせられました。
私は幼稚園~中学2年生まで、日本の学校に通っていました。中3の時に父の仕事の関係でアメリカのNY郊外へ引っ越すことになりました。 そこでは、幼稚園から中学校までに当たり前にやってきたことが全くありませんでした。
朝の会や、教室の掃除、日本のような運動会や学芸発表会、下駄箱もなければうわばき、体操着もない。 そして、教室では授業中にも関わらずガムは噛むし、先生だって机の上に座って教える。 鉛筆を貸すと、鉛筆の芯とは逆の方が噛まれて返ってくるのなんて日本ではありえないですよね。
英語はわからないし、友達もいないけど、でもアメリカの学校の自由な風土には感銘を受けました。今まで私がいた日本の学校はなんて窮屈だったんだろう。みんな同じでなくてよい。むしろ、みんなと違う方が良いことが、とても心地よく思えました。
結局、その心地よさが気に入り、嫌々泣きながら来たアメリカに大学卒業の8年間いることになりました。8年もいるとアメリカの文化もお腹いっぱいになり、日本の学校の文化が懐かしく、良いとこもだんだんと見えてきました。
映画では日本の学校は掃除や給食の配膳など生活に関わる教育まで行っていて、そのなかで、子どもたちは自分のことは自分でやったり、他者を想ったりすることを学んでいく様子が描かれていました。
協調性や一体感などを学ぶことで、子どもたちの成長につながることにもなるが、それが逆にイジメや個性をつぶしてしまうことになりかねない。そんなことにならないよう、葛藤しながら教育に携わっていかなければならないということを映画をみて感じました。
上映後には、監督の山崎エマさんと、「教育界のさだまさしです」と言いながら登壇された藤原和博さんという、おしゃべりの面白いおじさん!と思ったら、民間人で初めて公立小学校の校長を務められた方でした!そういえばテレビでもお見かけしたことありました。
長年、日本の教育について悶々と考えてきましたが、改めて小学校で子どもたちが、伸び伸び成長できるよう、大人たちは日々、葛藤しながら良い方向を模索し続けていかなくてはいけないと思いました。